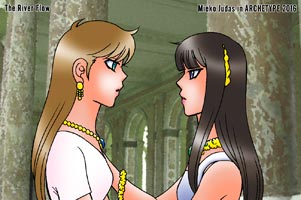 |
||||
|
ナイルと緑の芦辺
|
||||
|
#6
|
||||
|
The River Flow
|
||||
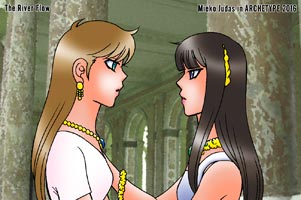 |
||||
|
ナイルと緑の芦辺
|
||||
|
#6
|
||||
|
The River Flow
|
||||
王家の中心的な家族に、久し振りに子供が生まれそうな空気は、王宮をも少しばかり騒がしくさせていた。無論後継者選びに関わる事でもあるが、今の段階ではそれより、直系と言える王家の血筋が絶えることなく、後に続きそうな様子を喜んでいるようだ。
ファラオの弟の嫡子である為、正確には分流の扱いだが、ファラオと王妃の間に子供が無く、またセイジの妻もファラオの妹であることから、誰も眉を顰めることなく、素直にその誕生を待つ雰囲気がそこかしこで感じられる。
そう、それは例外の無い王宮の気持だった。その日の昼下がり、大王母の部屋を訪ねた王妃とナスティも、その件について新たな知らせがあったと聞き、早速大王母に面会を申し込んだ。その時ふたりは、この場を立ち去ろうと廊下の端に消えて行く、ひとりの神官を見て「おや」と思う。セイジ付きのアヌビスがここに居たとを知ると、彼が何らかの朗報を持ち込んだに違いないと、ふたりは明るい顔で挨拶した。
「大王母様、御機嫌よろしゅう」
近年の大王母は、常にあらゆる方面に手を尽くし、エジプトの政治を陰で支える役目を果たして来た。故にいつも難しい顔で王朝の行く末を案じてもいる。その疲労が周囲に感じられることもままあるが、重圧に堪えられる精神は女性達の尊敬するところだった。そんな大王母が、ここ姑くは穏やかな様子でいらっしゃる。今日もその落ち着きと威厳の上に、本来の母親らしい優しさが見られ、娘達は話し易い雰囲気をより喜んだ。
「今見えていたのはアヌビスですね?、何かございましたか?」
とカユラが口を開くと、快くふたりを部屋に招いた大王母は、
「いえ、神官の集会の序でに挨拶に来ただけですよ。まだはっきりしていない事ですが、医師の見立てでは双児かも知れないそうです」
一度にふたり増えるかも知れない報告に、しかし前王妃として冷静な様子で答えた。確実な医術が存在する訳でもない為、それが事実かどうか、事実だったとしてもまともに育つかどうか、経験的にまだ喜ぶ段階ではないと考えているのだろう。だがカユラとナスティは興奮気味に破顔した。
「まあそうですか!、それは素晴しい知らせですわ。私もファラオも大いに期待しております」
「そうですね、無事産まれてくれれば、我が王家ももう少し余裕が持てましょう。セイジとシンは仲睦まじい様子ですから、まだその後も期待できそうです」
「私と王妃様はどちらもシンの実姉ですから、いつも助けになれるよう考えております、大王母様」
ナスティもそう言って、全力でシンの出産を助けたい気持を示した。本来自分等がその対象になる筈の王妃と侍女だが、現在の状況は、そんな個人的な立場の悪さを超えるものだと、ふたりはよく解っているようだった。それはある意味切ないことだ。特に大王母の目には、王家の女性として立派に育った王妃とナスティの、腑甲斐無い心境が垣間見えて切なく映った。
また、実はそれ以外にも、大王母には気掛かりに思う点があり、尚更大喜びする気持にはなれなかった。それについて、
「ですがね…、ナスティ、カユラ」
屈託なく明るいふたりの娘を前に、彼女は瞼を伏せて静かに語り始めた。
「嬉しい時ではありますが、よろしくない時でもあります」
「…どう言うことですか?」
その意味深長な言葉を耳に、若いふたりは確と大王母の話に耳を傾ける。そして、聞けば見えない所で何らかの、不穏な意識が存在することをふたりは知った。
「セイジがどう考えているかは知りませぬが、アヌビスの言動は得心し兼ねるところがあります。神官の考えですから、王家の存続を思ってのことでしょうが、血統が良ければ王朝が栄えると言うものではない」
「はい…」
つまりセイジ付きの神官が、この度生まれて来る子供に期待を持ち過ぎている、と大王母は感じているようだ。それが単なる身内贔屓でなく、血統にこだわる様子なのが解し難いようだった。
確かにエジプト王家には、近親婚の伝統が今も脈々と続いている。だがそれは、神の与えた特別な血を継承する意味ではない。昔はそう考えられていたが、まともに育たない子供が多く生まれた歴史から、今はただ、優れた知力と健康な体を子孫に与えたい、その為だけの習わしとなっている。それを知ってか知らずか、ファラオの霊的な力を取り戻せると唱える、アヌビスの熱狂はさすがに受け入れ難いものだった。
もう、伝説のナルメル王の血など広く散じ、最強のファラオだったラメセス二世王の頃には、他家や外国の血も多く入っている。血統が重要なのではなく、親からの遺伝が優れているかどうかの方が大切だと、王族の認識も変わって来ていると言うのに。
「軍馬の育成と我々は違います。単純な能力を極めれば良い訳ではありません。様々な人物が居てこそ王朝は成り立つのですから、あなた方もよくお考えなさい」
大王母はそう続けた。それは偏に王朝の安定と、一族の将来を思っての話だと、心から理解する女性達は、胸に手を当て膝を折って見せた。
「はい、確と胆に命じます、大王母様」
王家に次世代を担う者が生まれるのは幸いだが、それに因って不和が起こることは避けたい。何かにこだわり過ぎるのは、却って滅びを招くことだと、大王母の賢明な考察がふたりの心に染みた。
その部屋を後にし、ふたりの居住する別棟へと移動する廊下には、広く窓が開いており、今日は何処までも青く美しい空が見えた。穏やかな王宮の午後を彩る空の青は、晴れ晴れとした気持と些かの不安、ふたつを同時に表したようだとナスティは感じた。青は天の神々へと続く希望でもあるが、海水に沈み崩れ去る不安も孕んでいる。嘗てエジプト軍が、海に飲まれ総崩れになった話は、今も広く知られている事実だった。
そんなことを考えながらナスティが、
「大王母様の例えは素晴しい、何を仰りたいかよくわかりましたわ。私もジュン王子でも誰でも、ファラオに相応しい方がなられればいいと思います」
とカユラに話し掛けると、やはりカユラも王妃として、熱心に何かを考えている様子だった。
「ええ…、そうですが…」
けれど、その歯切れの悪い返事が少々気になった。つい先程までふたり、明るい話題に談笑していた筈だ。大王母の話を受け、新たに何か気掛りが生じたのかも知れないと、注意深くナスティはカユラに問い掛ける。
「どうかなさいました?」
すると突然カユラは立ち止まり、振り返ってナスティの双肩に縋るように手を置いた。
「ナスティ、どうか私の頼みを聞いて下さい…!」
「王妃様…?」
こんな風に頼み事をされたことはなかった。カユラの表情は特段思い詰めた様子でもないが、言葉の選び方からそれ相当に、深く考えた結果なのだろうとナスティは感じた。このところは日々明朗でいらした王妃様が、けれどお心の内では、大王母様のように常に状況をお考えなのだと。なのでナスティも確と、彼女の悩みを受け止めようと耳を傾けた。
その頃王宮の広間では、数カ月振りにタニスに戻って来た司祭長、カオスの壮健な様子を歓迎し、更に明るく賑わう声が聞こえていた。
「無事戻れて何よりだ、御苦労だったな」
「はい、こんな折にリビアが攻めて来るとは思いませんでしたが、大事に至らず安心致しました」
戦火に巻き込まれず済んだのは、誰もが本当に幸いだと喜んでいる。だが、カオスには目下のエジプトの問題をどうすべきか、重要な情報と意見を期待されてもいる。それも皆解っていることなので、帰還を喜びつつも、広間は凛とした緊張感に満ちていた。
集う会衆の中ファラオは言った。
「詳しい話は明日にでも聞こう。ただ、大まかな事だけ先に話してくれぬか。大司祭国の動向は、誰もが頭を悩ませている事ゆえ」
「わかりました、ファラオの仰せのままに」
長旅に疲れる相手を気遣いながらも、ひとつだけ話を聞かせてほしいと望む気持は、王朝に関わる者としてカオスも解り切った事。なので彼は当然のような態度で頭を下げた。もしファラオが「今日は休め」と命じたとしても、自ら大司祭国の件は一言話すつもりだったのだろう。するとそんな誠実な様子を見て、
「我々が早く知りたいのは、例のカルナク神殿の祭礼費用のことです。その概要だけ伝えて下されば、後は明日じっくりお話を聞かせていただきましょう」
と、ファラオの横に出て来た宰相も、カオスの疲労を考えそう付け加えた。
けれど万一、それが王朝側の考え得る最悪の結果だったなら、カオスの交渉は徒労以外の何でもなくなる。せめて彼の旅の疲れが、穏やかに癒える話なら良いのだが、と、会衆は心配しながら司祭長の報告を待っていた。そして彼が言うことには、
「ええ、その為に出向いたのですからな。しかし…、それが最も難しい話でございます」
どうも、特に良くも悪くもないと言った状況が感じられた。ある程度予想していた通りだったが、ファラオがそれについて尋ねると、
「良い条件は引き出せなかったか?」
「祭礼費用の一部を戦車などの物品で納める、或いは一年の間に分割して納める、或いは奴隷二千人を寄進せよとのこと。高額過ぎると言う点については、譲歩する意思は無いようです」
「そうか…」
結局方法を変えても良いと言うだけで、タニスの王朝から取りたい分は取ると言う、大司祭国の考えが判っただけだった。まあ、苦情するならもっと要求するぞと、言われなかっただけ幸いかも知れないが、
「それが大司祭の言葉なら何たること。エジプトの現状も弁えず、ナイルの水のように財が沸いて来るとでも思っているのか」
宰相は苛立ちながらそう口走っていた。役人を総括する宰相は、誰よりもエジプトの住人の暮らしが掴めている。大司祭国の支配力が衰え、以前より人も寄進も集まらなくなった事と、王朝の現状は無関係ではない。アメン・ラーの求心力が下がれば、エジプトで暮らしたいと望む住人の数も減少する。住人が減ればそれだけ労働力も税収も落ちる。それが解らないようでは、最早他国とまともに渡り合うこともできまいと、神官団の古臭い権威主義に呆れている。
するとそこでセイジも、
「逆かも知れない」
と、宰相に刃向かうのではなく、反対の視点でも考えられると話した。
「ナイルの水のように財の沸く国に戻そうと、祭を行う考えなのだろう。大司祭国はアメン・ラーのご威光に縋るだけの国、神の力を忘れられては困るのだ」
会衆は「成程」と相槌を打ちながら、どちらの説も理屈が通ることを思った。卵が先か鶏が先かと言う、有名な言葉は千年以上後に生まれるが、そんな状況は既にこの世界に存在している。そして宰相も、
「そうとも言えます、セイジ様。しかし祭礼を支えるのは神の力ではない。我々や諸候が寄進する現物の財ですぞ。大司祭国はそれを軽く考え過ぎている、市民や奴隷達の暮らしを守れなくなっては、エジプト自体が崩壊し兼ねないのですから」
セイジの話を引きながら的確に、この件の問題点を指摘してみせた。目に見えぬ、直接何をしてくれる訳でもないアメン・ラー信仰は、エジプトを強く象徴するものではあるが、民の生活にはあまり関係ないものなのだ。せいぜい葬儀の時に用いられる程度の事で、彼等の納めた税を多く寄進し、彼等の生活を向上させられないのではあんまりだ。そして、それも理解するファラオは深く頷き、
「全くだ。このまま言いなりになっていては、いずれ共倒れしてしまうだろう」
と、考え事を始めたように目を伏せた。ファラオはラーの息子、言わばアメン・ラー信仰を体現しなければならぬ立場だが、現状が果たして神々の望むエジプトであるかどうか、伝統と現実とを天秤に掛け、今はとても難しい判断を迫られていた。即ち神憑ったエジプトの栄光の歴史を取るか、人の能力を信じ現代的な治世を取るかと言うことだ。
何もかもが心許ない、太古の時代には神々の守護が何より必要だっただろうが、今現在は守護と言うより、アメン・ラー信仰は人としての教えである。蔑ろにすべきではないが、寄り掛かれる力のあるものでもない。それをどう表現すれば国を良くして行けるか、ファラオは改めて考えているのだろう。
王座にて静かに思考する兄を見ると、セイジはまた少し矛先の違う話題を続けた。
「そもそも大司祭国に独立支配できる力があるのか。彼等が平和を貪って居られるのは、このタニスの王朝が防護役になっているからで、我々の力が今より弱まれば、大司祭国も無事では居られないだろうに」
「その通りですよ、彼等は大した軍備も持ちません。なのに態度が尊大過ぎる、本来なら我々に頭を下げて戴きたいくらいなのに」
宰相が話に乗ってそう不満を漏らすと、そこで形の大きな軍隊長が口を挟んで来た。
「元々神官団は、そうして王家に寄生して来たのだ。今更態度を変えよと言っても意に解さぬだろう」
普段このような議事場では、滅多に発言しない厳つい男が、この点にはかなり悪い印象を持っていたことを知り、恐らく彼だけでなく、そんな者は多数居るのだろうと誰もが思う。言いたくても公には言えなかった理不尽を、この期に排除できるならそうしたい。そんな場の意識に任せ宰相が、
「ファラオの任命権を握られている限り、我々は大司祭の要請を聞く必要がある。その大司祭にエジプトの現実が見えていないのが、腹立たしくてなりませんな」
もう一声そう続けると、しかし、内部分裂を引き起こしそうな危うい流れに、カオスがやや強い口調で人々を諌めた。
「宰相殿、神官は神々の力と人を繋ぐ立場、神官団なりの理屈で動いているに過ぎませぬ」
「ああ、カオス殿を責めた訳ではないのだ、申し訳ない」
「いえ、携わる人間が愚かなのは認めます。だがアメン・ラーの力は、エジプトに取っては絶対であり絶大なものです。人心を束ねる象徴が存在してこそ、民はエジプトの治世を理解できる。アメン・ラーは我々の代弁者としての側面も持つのです」
つまり司祭長としては、これ程土地に根付いたものは、王朝に取っても安易に捨てることはできぬと、その不利益を案じているようだった。一言「アメン・ラーの御心」と言えば済むことを、ひとつひとつ理屈立てて説明するのは大変な事だ。まだこの時代には、信仰以外に法律と言う発想が存在しない。誰も神に代わる何かを見出せないでいるのだ。
「アメン・ラーが存在してこそのエジプト、なのですよ」
最後に重々しくカオスが言うと、それまで黙っていたファラオも、それに理解を示すようにこう応えた。
「難しい話だ…。神々の存在感は我々に計れるものではない」
その時、セイジはその遣り取りを耳に、
『そんな話を前にしたな。いやその時は、ナイルあってこそのエジプトだと私は言った』
シンを連れて出掛けた、ティムサ湖の緑の映像が甦って来た。ナイル川流域の豊かさは、正にエジプトの発展の源である。誰もがナイルの雄大な流れに心を寄せて来た。だが今語られているのはアメン・ラーと言う神のことだ。大司祭国の支配するテーベも、無論ナイル川の流域ではあるが、エジプト王朝の発祥はもっと下流の、メンフィスで成立したものである。北部と南部では多少文化が違う為、今は既に本来のエジプトとは違う姿になっていると思われる。
太陽神ラーはともかく、テーベの神であるアメン神にも支配されているのは、実は合点の行かない点でもある。トトメス王からラメセス王の時代が、あまりに強大で力を見せ付けた為に、いつの間にか当たり前にアメン・ラーと呼ぶことになったが。
本当はエジプトの民は全て、ナイルに帰属しひとつになれる筈なのに、神の名前に縛られているとセイジは思った。すると彼の思考を盗み聞いたように宰相が、
「国を二分するようなことがなければ、こんな厄介もなかったのでしょうな」
分裂後のエジプトの現状に溜息を吐いた。考える事は皆同じ、ならばそこを是正すべきではないかと、今度はファラオに代わりセイジが考える番だった。ここに集う誰より、エジプト以外の国々の神の在り方を、聞き知って来た経験があるのだから。
ところが、そこに思わぬ人物が姿を現した。その人は唯一セイジよりも、他国の事情に精通していると思われる男だ。
「厄介物の大司祭国など、もう断ち切れば良いではないですか」
と、突然会衆の後ろから出て来たのを見ると、今しがたここに到着したばかりなのだろう。ファラオを始め広間の人々の大半は、特に変わらぬ様子で彼を受け入れたが、カオスはひとり大いに驚いていた。神官職には就かぬと袂を分け、一介の役人として働き出した倅が何故ここに、と思うのは当然だ。
「トウマ、誰の許しを得てここに来た?」
カオスが訝しげな顔を向けて尋ねると、そう来るのもまあ仕方がないと、トウマは極力丁寧に、現在の己の恥ずかしくない立場を説明した。
「父上、私は今は、王宮役人として働かせていただいております。エジプト内外の方々に学んだ知識がございますから、ファラオより議会への出席もお許し戴いております」
そう聞いてカオスがファラオを振り返ると、確かにファラオは何も変わらぬ様子で頷いた。ファラオの信頼を何かしら得られたらしきことは、カオスにもそれなりに嬉しい事実だった。ただ、父親である彼には当然、トウマの持つ意思の危険性も理解していた。それが王朝に如何なる影響を与えているか、今後は注意深く見守らねばと、彼は一層司祭長としての責任を強く意識した。
但しこの場に於いてはさすがに宰相が、
「しかし、いきなり断ち切れと言うのは、それもあんまりな言動であるぞ」
トウマの物言いに苦言を呈した。結果的にそうなるとしても、現段階で簡単に言い切ってしまうのは、様々に意見交換する場に於いて配慮に欠けている。トウマとしては、単に停滞しそうな場面を転換したかっただけだが、言われればすぐさまその無礼に頭を下げた。
「失礼致しました、些か言葉が過ぎました。ですが、そう申したことには理由がございます」
頭を下げたけれども、トウマがまだ話を続けたそうなのは明白だった。大体彼はいつもそんな話し方をする為、会衆はもう慣れた様子で、彼の言う理由とやらを早く聞きたがっていた。そこには必ず何か新しい発見があると、既に周知のことにもなって来ている。そんな心境の変化はファラオも同じで、早速促されるままトウマに尋ねた。
「大司祭国を断ち切る理由とは?」
するとやはり、彼には誰にも持ち得ぬ意外な知識を、そこで盛大に披露してくれた。
「古のエジプト、ピラミッドの時代までは、ファラオこそ神と認識されていたのですよ。それを最初に神の息子と定めたのは、ピラミッド時代の神官達なのです。当時はホルス神の息子としていたようですが」
「な…!?」
トウマの予想通り、なのか、カオスも含め会衆が途端にざわめき出す。王家と神官、そしてアメン・ラー信仰は一体のものとして、古の時代から続いて来たエジプトの形だと、誰もが疑うことはなかったのだ。例えそれが嫌な柵だったとしても、始めからそうなのだから仕方がないと思っていた。
ただその中で、神官達はやや気まずい顔をして口を噤む。彼等はある程度のことは知っているようだ。無論トウマも神官の教育を受けて来たからこそ、エジプト史の謎に関心を持ったに過ぎない。
「何処からそんな事を」
驚きに言葉も無い人々を後目に、カオスが代表者のようにトウマに尋ねると、
「サッカラとギザのピラミッドを調べて判ったことです。どちらも盗掘に遭った為、内部に入ることができますから、書かれている言葉は全て読むことができます」
「恐れ多いことを…!」
ピラミッドに入ったなどと言う、トウマの行動に宰相が思わず声を挙げたが、今続けている話題の重大さに於いては最早、どうでも良い事だった。まあ、彼が極めて健康で聡明な様子を見れば、何ら罰のようなものは下っていないと、誰にも一目で解るだろう。歴代の王のモニュメント、ピラミッドを管理するのも神官団の仕事だが、下エジプトの神官の頂点に立つ司祭長が、トウマの行動を咎めないならそれで良いことだ。
それより、アメン・ラーの息子、ホルスの息子と、ファラオを「息子」の立場にしたのは神官だと言う、トウマの発見の方がカオスには痛かった。否、現在の神官団がファラオを騙している訳ではない。ピラミッド時代はもう千五百年も前のこと、当時の文書などは殆ど残っていない為、彼等も正確なことは知らなかっただけだ。時代により神官団が王族以上の、権力を振り翳して来た歴史を学んだだけで。
ただ、知らなかったとは言え、その事実はあまりにも印象が悪い。現に広間に集まる人々の、神官達に対する視線が変わったのをカオスは感じた。またそこで、
「ファラオが神だと…?」
と、ファラオ自ら、その発掘された事実に目を開き、トウマに子細を聞きたがる様子を見せると、人々もそれに倣ってひとりの青年に注目する。この事態が、ファラオの意識を神官団への嫌悪に向かわせないよう、カオスは神々に祈るばかりだった。そんな彼の気持を知ってか知らずか、トウマは有りの侭に、見知った事実を淡々と話し始めた。
「ええ、ナルメル王の上下エジプト統一の後、ピラミッド時代の初期、クフ王の頃は大繁栄を遂げていましたから、力あるファラオは神であり、それを支える神官団の力も強大になりました。ですがクフ王が逝去されると、息子のジェドエフラー王の即位の際は、神である王の息子として、ファラオを継承させるのが神官団の役目と、少し話を摺り替えたのです。恐らくジェドエフラー王が、クフ王ほどの才覚に恵まれた方ではなかったからでしょう」
トウマの説を耳にすると、会衆の中には深く頷きながら、酷く納得した表情を示す者も見られた。何故なら判り易い疑問として、ギザの巨大な三つのピラミッドがある。それぞれクフ王、二代後のカフラー王、その息子のメンカウラー王のもので、ジェドエフラー王のものは存在しないのだ。記録には短命だったとされているが、言うようにファラオとして頼りない存在だったからだと、理解し易い話だった。
しかしその、神である王の息子としてファラオを継承させたことを、摺り替えだとするトウマの言葉は、カオスには受け入れ難いものだった。後の時代の堕落は別として、当時は単に、体の弱いファラオを助ける為の事だったかも知れない。
「そのような、エジプトの歴史を愚弄する発言は許さぬ」
そこは厳しい態度でトウマに当たると、そう返って来ることも予想していたように、トウマは落ち着いて彼にこう話した。
「いいえ父上、愚弄などしておりません。私は大司祭国などと言う、ファラオの助けにもならない、権利を主張するばかりの神官団を離れ、父上が今王朝に於ける、本来の司祭の役割を担えば良いと言っているのです」
そう、寧ろトウマは、変わり行く時代に取り残されつつある、アメン・ラー神官団の有り様を心配しているのだ。その最たる大司祭国のような立場に、優れた司祭である父親が収まってしまうのは良くない。それはタニスの王朝の為にならぬ事だと、自ら宗教改革することを訴えていた。
「黙らぬか!」
「ああ、カオス様、そんなにお声を荒げなくとも」
珍しく声を荒げた彼に、宰相が近付きその心を宥めるように言った。だが誰の目にも、声の割に取り乱していないカオスの態度が、不思議に映るばかりだった。
それはそうだろう。希代の司祭長として尊敬を集める彼に、トウマの話す事の正しさが判らない筈もない。新たに出て来た事実を踏まえ、トウマの提案する道を選ぶもひとつの未来だと、彼ならあれこれ考えず理解できた。ただ、カオスとしては予備知識の無い人々の前で、不用意に心惑わせる話はしてほしくなかったのだ。それこそ王朝の判断が狂うかも知れない。
我が息子は類稀なる知恵に恵まれた。だがそれだけに、誰もが彼のように物事を理解できる訳ではないと、本人が気付けていない所がある。ファラオや神官達なら、何事も冷静に受け止めるだろうが、有りの侭の事実とは時に毒にもなるものだ。無闇に人を毒しては世論が荒んでしまうだろう。それをまだ社会経験の浅い息子は、把握し切れていないとカオスもまた案じている。
王朝を思う気持は同じであれど、同様に優れた父と子の間には、エジプトの揺れる未来が常に鬩ぎ合っているようだった。穏便に時を待つのが良いか、早急に体制を改めるのが良いか…。
「古の時代の、神官の行動がそのまま事実だったとしても、議場を混乱させて良いものではありませぬ。今の話は軽率でした。これだから倅は神官に向かぬと話した通りです。申し訳ございませぬ」
そう話してカオスが、ファラオの前に深く膝を折って見せると、さすがにこんな場面は具合が悪いと感じたのか、宰相が慌てて声を掛ける。
「貴殿が謝ることでは…」
今は大司祭国の問題を議論しているだけで、神官団を問題にしている訳ではない。トウマはエジプトに於ける、ひとつの根本的な誤りを指摘したが、それは大司祭国を説明する為の例であり、王朝の司祭長には何の非も無いことだ。なのでそう判る者には、カオスが会衆にこんな姿を晒すのはどうか、と思えたようだ。それはまたファラオも同じで、彼は司祭長の立場を気遣い、
「無論カオスのせいではない」
そう話して場の空気を落ち着かせた。
権力に集り私腹を肥やすような、悪名高い神官団の時代も確かにあった。しかしそうであってもなくても、エジプト王朝は栄えも衰えもした。時代や政治は王朝と神官団の、ふたつだけで全てが決まるものでもない。ファラオはそう学んで来たので、個人を責める意識は毛頭ないのだが、しかし、人々の知らぬ事実を詳らかにすることも、新しい時代には必要な事だと考えてもいる。
壁画やオベリスクなどに刻まれた、古の言葉は誰でも知り得るが、そこから古き良き王朝を想像するだけでは、昔に回帰したい意識ばかり育まれるだろう。過去と現在には様々な面で違いがある。過去とは違う何らかの成功を遂げる為に、今は常に新たな形を模索すべき時だった。そんな気持をファラオは、
「ただ、トウマの話は考えるべき主張でもあると思う」
簡潔にそう現すと、カオスも否定する訳ではなく、ただ慎重にお考え下さいと言葉を添えた。
「答を急ぐような提案には、安易にお心を動かしてはなりませぬぞ」
「わかっている」
ファラオとして即位してより八年ほどの間、サアメン王は日々この司祭長と共に歩んで来た。気心の知れた同士の会話は言葉以上に、意識を交流させているようだと人々は感じる。またそこでセイジが、
「だが知らぬまま居るよりずっと良い。私も何故、日々苦労して国を治めるファラオより、大司祭に神の権力が存在するのか理解できなかった。その起源を知って胸の閊えが取れたようだ」
改めてトウマの報告を評価する発言をすると、カオスはそれにも穏やかに節制を求めた。ひとつの閃きだけで動かすには、エジプトは深く広過ぎる土地だ。その全てが穏やかに進歩するよう促すのが、王朝の大切な役割でもある。
「セイジ様も、どうか見込み違いをされませぬように」
無論セイジもまた、ファラオ同様「わかっている」と示すよう、それ以上余計な事は言わなかった。
「恐らく見込み違いではあるまい、アメン・ラーは偉大なエジプトの心だが、神官団は人間だと理解しただけだ。それ以外に思うことはない」
カオスから見るに、ファラオとセイジの兄弟はこうした場では、決して不用意な発言はせず、王家の人間として相応しい人格になられたと感じる。さすがに王家の中心的家系の教育は優れていると、こんな時にはしばしば思うが、対して自身の息子は些か不躾な質に育ってしまい、司祭長として面目なくも感じている。この時も、セイジの言葉を耳にすると、
「そうですとも、神は神、人は人だと私も考えます。国を統治することと、アメン・ラーの力は直接関係はないのではと、常々思うことを述べたまでです」
率直なのは美点だが、謙虚さの欠片も無いトウマの話し方を見て、カオスは再度彼に態度を改めるよう求めた。
「それは、切り離してみなければ誰にも判らぬこと。憶測での発言は控えなさい」
こんな調子で常にファラオとも話しているのだろうか?。と、酷く心配にもなった。
けれど言葉は鋭く聞こえても、誤った知識や偏狭な考えは持たず、冷静で思考の優れた息子だとも知っている。ファラオならば、或いはセイジならば、何を耳にしても動揺はしないかも知れぬと思った。現に己が王宮を離れていた間、彼は随分信用されたようだとカオスにも判る。
「まあそうですね。私は人ですから神のことはわかりませぬ。へブライ王国にも神は存在しますから、決して軽んじている訳ではないのですが」
トウマが少しばかり大人しく返すと、それには納得してカオスも厳しい表情を崩した。やや問題に感じる点はあれ、この先王朝の為に良い働きをしてくれるなら、それが父親としては本望でもある。
「さもあらん。神とは我々恵まれた者より、民にこそ必要な存在であることを忘れぬように」
カオスの広間での話はそう締め括られた。本来の神官とは、ある面では王家や王朝よりも、エジプトに生きる全ての人々を庇護する職だなのだと、その言葉からは誰もが感じ取れた。そして形は違えど出来る限り、我が倅にもその事実に背かずにいてほしいと、カオスは伝えたかったようだ。
求むるが故に神は在る。持たざる者こそ神を求むる。
信仰とは何かを、この時代に深く考える者は居なかっただろうが、王朝の神官として日々考える内に見えて来る、その存在は人々の理想だとカオスは感じている。目指す理想なくして人は進歩しない。それは例えエジプトが滅びたとしても、変わらぬことなのだろう。
「ヘブル人の神はヤハウェと言うのだろう?。何でも人々に厳しい戒律を授け、従わぬ者は子々孫々に渡り安楽を許さないのだとか」
トウマがヘブライ王国と言う言葉を出したので、セイジが聞き知ったそんな話を語ると、アメン・ラー信仰の大らかな庇護とは全く違う、他国の様子に会衆は少しばかりざわめいた。
「何と恐ろしい…。かの国の民は、何故そんな神に従おうと思うのか?」
「厳しさも良き教育と言うことではないか?」
「成程、一理ある。そうして戦乱を生き延びようとしているのだろう」
それもひとつの理想の形だと、変わり行く世界情勢の中で、人々が理解して行く日は近いのかも知れない。
王宮に司祭長が戻り、普段の安定を取り戻した数日は、特に外部の問題も無く落ち着いた日々だった。
無論大司祭国への回答はまだ決定していない。攻め込んで来たリビア兵の処理も済んでいない上、セイジの指摘した海の民と言える集団の動きも追っている。だがひとまず戦争状態から解放され、本来居るべき人物が戻って来たのは、ファラオに取ってどれ程心の休まる事だったか知れない。
難しい時代の舵取りをするのは重労働だ。若く健康なファラオではあるが、常に周囲からその健康状態を心配されてもいる。病は気からと言う概念も、既にエジプトの医学には存在した為、政治的な事以外ではなるべく、彼のストレスになる事は避けたいところだ。
けれど、局面によってはどうしようもない事もある。常にファラオの側に仕え、ある意味誰よりファラオを心配しているカオスだが、今は決断しなければいけない時だった。その日の午後、彼は宮廷の広間が静かな頃に、ファラオの前に出てこう言った。
「私は今一度、明日か明後日にでも、大司祭国へ交渉に出ようと思います」
まだタニスに戻って十日程だった。この件に関しては確かに、王朝としての意思を決めかねており、まだ具体的な方針も全く定まっていない。向こうの神官団と幾度も話を交わし、より良い条件を引き出せれば、それだけ議事的決定はし易くなるだろう。だがしかし、
「何故、それほど急いで出掛けるつもりか?」
さすがにファラオはカオスの心身に不安を感じた。実父であるオソルコン王とほぼ年の変わらない、カオスはこの時代にはもう、あと数年で現役を退く世代のひとりだ。長期間土地を離れていただけでも、生活の不自由や苦労はあっただろうに、殆ど休み無くまた上エジプトに出向くと言うのは、通常なら受け入れ難い話だった。けれどその後続けられた話を聞くと、ファラオも頷くしかなくなってしまう。
「私はエジプトの司祭として、神々への信仰自体に疑問を抱かせるような、大司祭国を説得すべきだと思うのです。でなければ皆の心もまとまりませぬ。このままでは」
彼が戻ってより、議事場の広間は常に活発な議論が行われ、それは一見良いようにも見えるが、トウマの話した「神の息子」の経緯を知ると、宰相を始め役人達は神官団そのものに疑問を持ち、現状の是非を問うようになっていた。変わらず神官や信仰に重きを置く者も無論居り、意見が対立或いは平行線となって、議論が白熱しているのが実情だった。
新たな時代の為に、古い価値観への議論をするのは大いに結構。だが、近々の問題を抱えた不安定な情勢の中、国を先導する役職に就く者達が、意見を違え纏まらぬことがあっては、有事の際にあまりにも心細いとカオスは感じたようだ。
これまでは神官以外は殆ど、エジプト政治の宗教的側面を知ろうとする者は無く、役人達は寧ろ民人より無関心な程だった。彼等に取ってアメン・ラーは、逝去された過去のファラオより希薄な存在だろう。それは当然、彼等の苦労を労ってくれるのはアメン・ラーではなく、国の為に的確に権勢を揮う王なのだ。信仰と治世は全くの別物だと、特に国が分裂して以降は広く考えられている。
だが本当にそうだろうか?、と、カオスがトウマの前で語ったように、人は確かな物質より、形の無い曖昧な物にこそ夢や希望を抱き易い。神官が治世に関わるべきかどうかは別に、神官団や信仰を嫌悪する流れは、大司祭国に対し態度の硬直を招いてしまう。理解なく拒否するだけでは何も解決しないばかりか、本来エジプト王朝が持つ財産の、大きな部分を大司祭国に取られてしまうことになる。
人々の不和、国の対立、王朝の損失、幾つかの面で、今すぐ何か解決策を見い出さねばと、カオスが決意した気持はファラオにもよく解った。
「…そう、今はアメン・ラー信仰と実際の治世が、ほとんど結び付かぬものになっている。神々と一体であった昔の姿は余も想像できぬ。それでは皆を納得させるのは難しい」
「ええ、だからこそ私が橋渡しをしなければならぬのです」
故に彼の申し出を退けることはできなかった。司祭長は王朝の精神的支柱であり、出来る限り王朝の中心で働いてほしい人物だが、それだけに、彼でなくては出来ない議論や交渉事もあるだろう。
「わかった。良き道が開けるよう願っているぞ」
ファラオは引き止めたい気持を飲み込むと、一国の王らしく落ち着いた様子でそう送り出した。
またその夜、王妃カユラに幾度も説得され、ファラオはひとり寝所である人が来るのを待っていた。王宮にて政治的決断をするのも責務だが、王家の一員として他にも果たさねばならない事がある。これまでは政治以外の面で、周囲の者を気遣わせることはあまりなかったが、状況の変化により、王妃が切に懇願する内容も理解できるようになった。即ち、侍女に子供を産ませると言うことだ。
権力や面子の話ではない。前途の通り妾を集めた後宮を廃止した為、ファラオが無数の子孫を持つことはなくなった。今やエジプト王家の血筋を守るには、限られた中で確実に、血統の良い後継者を排出しなければならない。その責任を弟にだけ負わせるのは、やはりどうかと思うようにもなった。
世界も変わって行くが、王宮の様子も変わって行く。ファラオはひたひたと近付いて来る、軽い足音にじっと耳を澄ませていた。
つづく
コメント)前のページで征士と伸の話に戻った、と思いきや、このページはまたさっぱり出て来ない(^ ^;。迦雄須と当麻の話がメインになっちゃったけど(あと私の好きな遼ナスだ)、構成上どうしようもないのよ〜。次のページはまた出て来るから勘弁して〜。
ところで、やっと解説が入れられるページに来たけど、何を書きたかったのか忘れた!。今急がし過ぎて、小説を書き進めること以外にあまり何も考えられない…、それもこれもスマホとタブレットのせいだ!。
あ、ひとつ思い出したのは、征士と伸が訪れたティムサ湖のこと。出エジプトでモーセの前の海が割れた、と言う話の舞台です。いや本当は他にバーダビル湖と言う候補地もあって、そっちの方がそれらしいんだけど、植物が全く生えてないからお話的に却下した(笑)。どちらも紅海に繋がってる関係で潮の満ち引きがあり、水が引いてると陸が現れる場所です。
と、最後にもうひとつ、秀を女性にしてるから口調がすごい違和感だよね、自分で書いてて思う(^ ^;。他の女性達よりは砕けてるけど、王族だからさすがにあまりはっちゃけられない。この話ではあまり関係ないけど、女性にしたのは理由があるのでお許し下さい。今年中にはわかりますから…
GO TO 「ナイルと緑の芦辺 7」
BACK TO 先頭