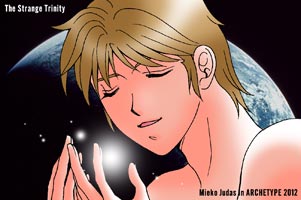 |
||||
|
三界の光
|
||||
|
#9
|
||||
|
The Strange Trinity
|
||||
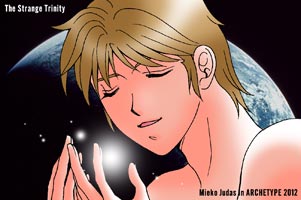 |
||||
|
三界の光
|
||||
|
#9
|
||||
|
The Strange Trinity
|
||||
しかし、今頃相手を理解しても、もう遅いかも知れない。
今横に立つ年の近いセイジ、即ちデシモ・セイジ・ダテは、もうすぐ亡くなった元首と交代し、現人神のように手の届かぬ存在になってしまうのだろう。そうでなければ、無理矢理自分をここに連れて来た理由が解らない、とシンは暗に考える。こうして様々なことを普通に話せる時間が、この先長く続けば、その時間の分だけ理解してあげられると思うのに…。
すると、話していたふたりの元に再びトウマが姿を現し、誘導するようにその手を拱いた。
「元首の交代式を行う」
その合図に促され、セイジとシンはグレーの床が続く更に先へと歩き出す。ホールの先の出口とも入口とも知れない、別の空間への通路を抜けると、そこはホールと同じく円形で、ドーム状の屋根を持つ特殊な小部屋だった。その中央に、棺と思しき黒の木箱が安置されていた。横にはトウマが厳かな様子で立っていた。
セイジはそろそろと棺に歩み寄り、その中に横たわる人を暫く眺めていた。けれどシンにはとてもそんな気にはなれなかった。セイジに取っては親のようなものかも知れないが、自分には見たことも聞いたこともないセイジ・ダテだ。ただでさえ葬儀の雰囲気は、悲しい気分を引き出して来るのに、必要以上の感情移入をしたくなかった。部屋に入って立ち止まった場所から、シンは一歩も前に進むことはなかった。
ただ、今セイジが何を考えているかを思う。ある意味棺の中の死体は彼自身のものだ。若い体の中にまだセイジ・ダテは生きているが、老いて死んで行った過去の元首の歴史も、当然彼等の中に存在するだろう。彼等の悲しみは時と共に幾重にも重なり、この部屋に刻み込まれているようだった。
それとも、幾度も経験すれば慣れることだろうか。或いは一代一代を「仮の死」と受け止め、特に悲しむことはないのだろうか。今見えている若いセイジは、悲しいと言うよりは仕方ないと言った趣で、神妙な表情を見せているけれど。
それにしても。
もし元首と呼ばれる人物が認知される存在なら、その葬儀は各居住星をあげての一大行事だろう。しかし実際は僅か数名の者が立合うだけで、棺は寂しく埋葬の地へ送り出される。これが三百年の間に、七回繰り返された連合元首の葬儀なのだ、と思うとシンには、哀悼の念より苦笑が込み上げて来るようだった。それもそうだろう、一般市民の葬儀にも参列者は多く居るものだ。秘密裏に、無理に長く生きることは決して幸福ではないと判る。
個人に取って決して幸福ではない。けれど伊達征士はこの道を選んだ。自身を含めより多くの地球人を守る為に。それが毛利伸の望みでもあったから。
そこで改めて考えると、自分のオリジナルである毛利伸とは、善意こそあれ罪作りな人間だと感じた。こうして何代にも渡りセイジを生かし、一度完全に死亡したトウマを復活させ、自らの理想を盛り込んだシステムを守らせている。過去のたったひとりの人物の、特に明確でない未来のヴィジョンを実現する為、彼等が絶対服従で働く状況は、シンには多少胸が痛んだ。それでは新たな僕は何をすればいいんだろう?、と。
否、彼等は話してくれた。全て毛利伸の愛情から始まったのだと。
愛情とは、何だろう?。
シンが考えている内に、セイジは立ち上がり棺の傍から離れていた。そして再び自分の横まで戻って来るのを、シンは無意識に目で追っていた。その視線にはセイジも気付いただろうが、彼は何も反応せず、場に流れる空気に合わせ黙っていた。
そう、確かに空気が微妙に変化した。これから元首の交代式が行われる。シンはこの後に起こる何らかの事態に備えるように、自然と拳を握り締めていた。例え「今の自分に満足している」と言ったセイジでも、生きた人間である限り、簡単に悟りを開けるものではないだろう。これからずっとこのポリヴの中で、ロボットと機械類を相手に一生を過ごすとなれば、今の内に吐き出したいことも何かしらある筈だ。以前、自身の不満をぶつけて来たことがあったように。
けれどセイジはそんな素振りも見せず、ただ難しい顔をして前を見ていた。まさか自分に「共に一生留まってくれ」とは、流石に言わないだろう。けれどそんな無茶な要望も、口に出すだけならいいのではないか、とさえシンは思っていた。それほどに今のセイジの様子は不可解だった。
今なら、君の言葉をみんな受けてあげられるから、と、シンは言葉にせず念じてみたが、過去の毛利伸のような能力は、今は存在しないことを知るだけだった。
様々な考えが、シンの頭の中に生まれては消えて行った。感情のままに生まれる素直な思考は、どうしたらこの遣る瀬ない状況を変えられるか、誰もが心から納得できる形にできるか、そればかりだった。成るようにしか成らない事かも知れないが、過去の悲しみを見るばかりの葬儀など、人の精神に良からぬ行事は変えて行くべきだ。社会に対する絶対的秘密主義も、出来ることなら変えて行くべきだと思った。
ああ、それが僕の役割かも知れない。
シンは思う。それが新しい自分の愛情かも知れないと。
セイジの別れの挨拶が済むと、トウマは足元にある棺を軽々と持ち上げ、葬儀用に設置されたコンベアーの上に乗せた。それは水の上の小舟が揺られる如く、非常にゆっくりとしたスピードで三人の見詰める前を進んで行った。棺はそれから、ドームの部屋の更に奥の暗がりの中へと流れて行く。一般の葬儀でもしばしばあるが、宇宙へ射出する装置と繋がっていることが、それとなくシンには判った。
但し未知の宇宙へと流す「宇宙葬」ではない。
「月だ」
と、一言だけセイジが教えてくれたが、その直後にジェット噴射の音が鳴り響き、それ以降の会話は続かなかった。
棺を乗せたポッドは決められたルートを辿り、月の裏側に在るセメタリーエリアへ到着する。その様子はポリヴの中からは見られないが、シンは音を頼りに想像した。今、ここから射出されたポッドは、ポリヴを抜けて真直ぐ月へと向かって行く。眼下には何より大切な地球が見えるだろう。その青い光を受けながら、到着する月はいつも地球の周囲を大事そうに回っている。もし月に心があるなら、それは正にこの世界の元首の心だと思う。
その場所は、辛い責務から解放されたセイジ達の安息の地。そして恐らくオリジナルの毛利伸も、更に初代のロボット、プロトタイプナスティのボディも埋められているに違いない。シンが今願うことは、ただこの三百年の過酷な歴史が無駄にならぬように、との気持だけだった。自分はともかく、この宇宙に広がる多くの人の幸福が、長続きする為にも大切なことだった。
その時、この建物の何処かで扉が開く音がした。そして自分達の方へと、少しずつ近付く誰かの足音が聞こえた。
シンとセイジがここに着いた時は、エアポートと内部の部屋を仕切るエアロックが開いたが、その音にしては軽過ぎるようだ。その他には、彼等の来たルート上にエアロックらしきものは無かった。そもそもトウマの他には、元首ひとりしか存在しないこの場所に、多くの出入口を用意するとは考え難い。と言うことは、既に内部に滞在していた別の誰かがやって来た、と言うことだろうか。
今、視界に居るのはセイジとトウマ、その他には本来誰も居ない筈だった。亡くなった元首の亡骸さえも、もう月へ送り出してしまった後だ。今さっきその射出音をこの耳で聞いたばかりだ。ならば考えられるのはただひとつ、とシンは閃いた。
他にもまだセイジが居るのだと。
ここに入って来た時にも聞いた、気が遠くなるような足音の反響。幾重にも重複し、無闇な緊張を煽るその音が段々と近付き、その人がもう直ぐこの部屋にやって来ることを告げる。
音が、徐々に大きくなって来る。間近まで近付いて、そして部屋の扉が開いた。
「お父さん!!」
シンは、その姿を見るなり反射的に駆け出していた。
「お父さん!、何でこんな所に…」
入って来た人物に迷わず抱き着いてシンは言った。それまで落ち着きを保っていた頭が途端に混乱する。何もかも空白になり、これがどう言うことなのか理解できなかった。ただ十余年も離れて暮らしていた、父親に久し振りに会えた喜びと、こんな場所で会えたことへの困惑があるばかりだ。
「シン」
と、その人は彼の体を優しく抱き竦めて言った。自分が安心して縋れる唯一の存在を前に、シンが涙しない筈もない。この数日、否このひと月少々の間、彼に取って辛い経験が続いたせいもあるだろう。後から後からこみ上げて来る、喉を締め付ける咽びが止まらなくなった。そして言葉も綴れず泣くばかりの彼の頭を、ずっと撫でてくれている掌は、正しく自分の父親のものだとシンは確信した。故に、更に安堵して暫く身を預けていた。
ところが、一気に溢れ出した涙が多少収まった頃、シンはそっと顔を上げて愕然とした。
「!?」
以前より大分赤味掛かってはいるが、その人の瞳は紫色をしていた。
幼かったシンが見て触れた父の記憶は、今も鮮明に彼の中にあるものだった。しかしそれは意外と曖昧で、漠然としたものだったのかも知れない。今彼が目の前に見ている、確かに自分の父親であるその人の顔は、木星で、ステージの壇上に居たセイジを見た時と同じような、何処か割り切れない印象を与えた。
父の顔は、伸ばしていた髭や、髪、眉こそ白くなったものの、自分をここに連れて来た人によく似ていた。
セイジを最初に見た時、隣のせっちゃんが成長した姿のように思えたが、父はセイジが更に年を重ねた姿そのものだ。棺の中の前の元首を見ていたら、シンはより恐ろしい思いをしたかも知れない。例え個性が違うにせよ、こうして同じ人物が何代も、世代を重ねて生き続けていることを彼は、この時本当に理解できたのかも知れない。
「もう一度会えて良かった」
シンの父親、セイジは、自身にすっかり体重を預けているシンから離れ、そう言った。改めて両手をシンの肩に置くと、そっと額に唇を寄せた。そしてふたりの様子を見守っていた、自分より若いセイジとトウマの居る方へ、ゆっくりと歩き出した。
「元首を交代する。如何なる時も人間を優先する、元首コンピューターはこれを承認した」
トウマの宣言が、静かな部屋の隅々まで響いている。その中で、
「私は知っての通り宇宙病に罹っている。すぐに代替わりするかもな、悪いが」
父親のセイジは、冗談でも飛ばすような明るい口調で、自分とは違うセイジに声を掛けた。その言葉には同じ人間であるが故の哀れみと、同じ人間への優しさが感じられた。シンは、父がこれから自由な生活を失い、望んだ訳でもなく惑星連合に身を捧げる余生を送ることに、心のまま悲しんで良いものか迷い出す。何故なら父は今、誰よりも後に替わるセイジを気遣っているからだ。
しかし若いセイジは、「解っている」と示すような笑みを浮かべて返した。
「気遣いはいい、オッターヴォ。私はこの年のセイジ・ダテに生まれただけ幸運な身だ。いや、あなたも」
「フフ、そうだな」
何故若いセイジが父を名前で呼ぶんだろう。父はオッターヴォ、あのセイジの名前はデシモ…。そんな疑問が今更湧いたのがリアルだと、シンの瞳には再び涙が溢れ出す。
名残り惜しむようにゆっくり踵を返すと、父親はこの部屋の更に奥へと通じる扉へ歩き出した。それに合わせ、ポリヴの管理者でもあるトウマが、影のようにその後を着いて行った。ふたりが扉の向こうに消えてしまう前に、
「ありがとう」
父は一度振り返って言った。それがシンの耳にした、彼の最後の言葉だった。
扉が閉まった途端、シンはその場に座り込んでしまった。突然の脱力感、突然の喪失感、けれど決して不幸ばかりではないこの状況に、まだ思考や感情が追い付けない。頭の中で父の言葉が、鐘の音のように谺して、ただ自分を包んでくれているのを感じていた。またセイジはその横で、彼が落ち着くまで身動きもせず見詰めていた。
スワニー・マーク2の黒い機体がポリヴを抜け、今は眩しく感じる宇宙空間に出た。あれから、父の姿が消えてしまってからどのくらい経ったのだろう。魂が抜けたような、いつになく重く感じる体をシンは、座席の上でだるそうに捩った。
今、何食わぬ顔をして同乗しているセイジは、その間殆ど話すこともなく、ずっと彼を見守ってくれていたようだ。人が思い切り泣きたい時に、宥め賺す言葉を掛けられても鬱陶しい。セイジはそれが解る人なのかどうか、取り敢えずシンは、彼については「鬱陶しくない人」と認識を改めることにした。
否、今日のこの出来事は、確かにある程度相手への見方を変えてくれた。ただそれでも、急に百八十度印象が変わるほどではなかった。何故なら彼はせっちゃんでも父でもない、あくまで別の個性だと自ら主張している。ならばいきなり好きになることもない。
だが、本当に大事な時に無理矢理でも、ポリヴに連れて来てくれたことには、感謝せざるを得なかった。それでこそセイジの役目を果たしたと、シンが評価できる点のひとつだ。このセイジも、それほど嫌な奴じゃない。そう思えるだけで今は充分かも知れなかった。
『もう、お父さんには会えないんだろうか…?』
船は今、丁度地球と月が美しく見える宙域を飛行している。父はいつも、宇宙の素晴らしさと可能性を自分に教えてくれた。遠く離れれば離れる程、全ての始まりである月と地球は愛おしい。きっと父はそれを伝えようと、自分に語り掛けていたのだろうと思った。当たり前に豊かさが存在すると思ってはいけない。何もかもそれを守ろうと努力する人間あってのこと、今の地球圏と植民星も皆そうなのだ。
そしてシンは月の反対側にあると言う、代々のセイジが眠る場所を思いながら、前の元首はもうそこに到着しただろうか、などと考えていた。考えている内にウトウト眠ってしまったが、記憶が曖昧な中で月基地の宿泊施設には戻っていた。
彼はもう、夢であってほしいとは思わなかった。彼の心の中の何かが解放されたこの夜。そして目覚めた後には、世界が少し変わっているかも知れない。恐らく何も悩まなくていい方向へ…。
朝、教官と研修生は一週間の研修を終え、月基地の職員に挨拶をして回っていた。聞いた通りここは、地球に取って重要な情報が中継される、主要拠点のひとつと理解できたが、基地内の雰囲気は相変わらずのんびりしており、離れる時もまるで転校生を送り出すような、明るさと賑わいを見せていた。退屈凌ぎに研修生を受け入れると言う話は、強ち嘘ではないのかも知れない、とシンとナアザは思った。
そして、地球に戻る三人を乗せた輸送機は月を飛び立つ。短い間だったが、貴重な経験をさせてくれた月基地が、あっと言う間に見えなくなり、シンは彼だけの持つ感傷に浸っていた。恐らくこれでパイロット研修も修了だろう。本当に色々なことがあったが、今、それなりに気持良く前を向けるようになったのは、その間出会った全ての人のお陰だと。
先輩、教官、リョウとシュウ、事務次官のセイジ、ロボットのトウマ、月基地のオペレーター、今元首の座に着いたお父さん…。
嬉しい出会いばかりではなかったけれど、それでも今は穏やかに現実を受け入れつつある。全ての人の思いが、同じひとつの「地球の仲間としての調和」に向かっていると、最後には気付けたからかも知れない。自分の周囲には幸い、嫌な考えを持つ人は現れていない。それだけでも充分幸福なことだとシンは考えていた。
「何かあったのか?、月で」
その時、隣の座席からナアザが覗き込みながら言った。
「いや、別に何もないです先輩」
「そうか?。考え込んでいる割に、妙に楽し気な顔をして」
「楽し気…?。じょ、冗談じゃないよ!」
そう言って不意に息を巻く、シンの様子にナアザは驚いたが、それ以上にシン本人もハッとしていた。
「あっ、すいません」
思わず先輩にタメ口を使ってしまった。その時彼の頭の中で、反論したい何らかの考えが極みに達していたのだろうか。珍しいことだと、
「何だ?、どうしたんだ?。やっぱり何かいいことがあったんだろ?」
「いや別に、ホントに何もないですって…」
ナアザはもう一度尋ねたが、シンは苦笑いするばかりで答えなかった。実はその時、
『「自分は人殺しかも」って、悩まなくなったのはいいけど』
そんなことをシンは考えていた。まあ、それもいいことには違いないが、ナアザが期待するような話題でもなかった。がっかりされても困るので、彼は敢えて話さなかったけれど。それ以上に、セイジに関することを楽し気に考えていると、思わぬ指摘をされて慌てたのだ。そんなつもりはなかったが、自分はそんな表情を見せていたのだろうかと。
それは恐らく、まだ残る口惜しさだ。
否、セイジ自身が話したように、せっちゃんとセイジは同じクローンとは言え、別の存在だと今は知っている。自分はせっちゃんの望んだ未来を大切に、このアストロノーツの仕事を続けようと考えている。それが償いであり、気に掛けてくれる父への気持でもある。これらのことは、事務次官のセイジには何ら関係のないことだ。
父もまたクローンのひとりだったが、やはりせっちゃんやセイジとは違っていた。あのセイジがデシモと呼ばれるのに対し、オッターヴォと呼ばれ区別もされていた。また亡くなった元首はセッティモと言った。自分が生まれる以前の歴々、真面目に自分のことを思ってくれた人々は、全て自分に取っての父親だとも思う。ただ年令の近いセイジには、流石に父親のように慕う気持は生まれない。
なのに。セイジだと言うだけで、今は妙な意識を持つようになってしまった。過去の伊達征士と毛利伸がどんな関係だったとしても、今の自分には関係ない筈なのに。
『これからどうなって行くんだろう、僕は』
関係ない筈なのに、心が彼の方へ流れて行くのは、予め細胞に刻まれた予定だったのだろうか?。
けれど恐怖感が薄れた今はそれも、さして不快な状況とは思えなくなっている。悔しいがそれでいいのかも知れない。セイジ達の側からは、正にそうなれば良かったのかも知れないと、落ちる所に落ち着いてシンは目を閉じる。そして改めて、
『あのセイジは…』
恐らくこれから付き合って行かねばならない、デシモ・セイジ・ダテについて考えた。
もし「君なんか嫌いだ」と言ったら、彼はどんな行動に出るだろうと思うと、何故だか面白くも感じた。そんな意地悪をするつもりはないが、彼の一途な思いの激しさには、ついからかいたくなるような面が垣間見れる。常に大人振った態度でいるだけに、それが崩れる顔を見てみたいと思ってしまうのだ。デシモは多分、中身は面白い人間だろうと思えるからだ。
果たしてそれは、過去の毛利伸も感じたことだろうか?。
もう誰にも判りはしないけれど、こうして古の時代に生きる自分達を思いながら、更に未来を歩いて行ける面白さも存在する。その為の産みの苦しみなら、この四十日ほどに及ぶ出来事は水に流そう、とシンは納得するしかなかった。
そう、ここ最近の彼の慌ただしさは、全て隣のセイジ少年の転落事故が原因だった。管理をする元首とコンピューターは、シンの精神的健康を損ねることを嫌い、計画的にそれ以上の経験をするよう仕向けた。新人研修の各作業、他のセイジとの出会い、家族は代替ロボットであると明かすこと。元首交代だけは予定外だったが、それが現在に至る状況だった。
そしてそれは結果的に成功したと言えるだろう。シンはもう、小さなせっちゃんについて悩まない。無論シンが彼を良き思い出としてくれることは、セイジ達にも有難いことだ。ただ、本来は年の近いセイジが、段階的にシンを理解させる役割だった筈が、それについてはあまり上手く行かなかった。偶然の元首交代で状況が落ち着いたが、今ならば、若いセイジには荷が重かったと、年嵩のセイジは考えているに違いない。
他に動かせる駒が無かったのだ。父親であるセイジはそれを、ほんの僅かな時間でやってのけたが、それは共に過ごした時間と信用あってのことだ。当時全くの部外者だったデシモが、始めからシンの信用を得られるかは、同じ顔をしている分だけ難しかった。例えコンピューターや社会構造が完璧でも、上手く行かないことはあるものだ。
シンとオッターヴォの揺るぎない絆。或いはシンと、まだ名を持たないせっちゃんの仲の良さが、デシモは羨ましかった。それが元首の計画の敗因となったが、結果が良ければそれも無駄ではない。長くシンに関れなかったデシモについて、まだ充分な時間が残されているのが幸いだった。
これからはきっと、彼等の時代になるだろう。
三人の乗った輸送機は、有り触れた日常の繰り返しのような顔をして、何事もなく地球の宇宙港に到着した。そこには研修中のパイロットも、研修中の宙港作業員も居ただろうが、人の活動は止まることなく続いている。まるで惑星が太陽を回り続けるように。
その太陽が、宇宙港のアスファルトを明るく照らす中、シュテン教官が解散の挨拶をする。
「これで研修は終わりだ。ふたりともよく働いてくれた。休暇中に正式な配属の連絡があるので、それまでは自宅に待機すること。以上だ」
その、いつも快活で爽やかな彼の様子が、もう見られなくなってしまうと思うと、シンは少し淋しい気持になった。すると、
「あんたの顔もこれで見納めと思うと、多少淋しい感じもするな」
ナアザがシンを代弁するように、ほぼ同じ気持を話し出す。ちょっとしたことだが、同じ意識を持てる仲間とはいいものだと、改めてシンは思う。アストロノーツを目指したことが、間違いではなかったと気持良く感じられる。
するとシュテンはこう続けた。
「いや、何処かでまた会うことがあるだろう。この仕事は偶然の出会いが醍醐味とも言える。何光年も飛び回りながら、距離も時間も隔てて再会するのだからな」
「何光年か…」
その時、シンは父から聞かされたあの言葉を思い出す。
『宇宙は広く、わからない物やわからない事が沢山あるんだ。
きっと何かが自分を見付けてほしくて、
おまえを待っているから、アストロノーツになるんだよ』
同じだと思った。父の言っていたことは確かにそうだと、納得すると共に、それはセイジとシンがまた出会うことでもあったのだろう、と今はシンにも解る。出会うと言う出来事は大切なことだ。それがなければ何も始まらない。人の繋がり、人間の築いて来た社会こそが大切なのだから。
その中に、今も僕らは生きていられる。
「今度会う時はただの同業の先輩だから、お手柔らかにな?」
シュテンが最後にそう言って笑うと、研修生ふたりも、
「了解」
と敬礼して笑った。シュテン教官も、ナアザ先輩も全て、また何処かで会えると信じていれば、必ず会えるのかも知れない。それがアストロノーツと言う職業だ、と、シンは抜けるような空の向こうに、元首の心を重ねて見ていた。
その数日後、心待ちにしていた連絡がシンの家に届いた。
「…配属が決定致しました。惑星連合植民星開発省の、監査次官の専用機パイロットに任命されました」
テレトーク画面の女性は、淡々とした口調でその内容を読み上げていたが、シンはその内のある単語に、息を飲むように聞き返した。
「専用機、ですか」
「はい。所属部署は惑星連合地球本部、第一操縦課第九隊、階級はシン・モウリ三尉となります」
更に説明は続くも、専用機への配属が嬉しくて、肩書など最早シンの耳には入っていなかった。彼は忽ち、数日前に訪れた小型機の格納庫を思い出す。新型、旧型、形式は様々あれど小型機には、パイロット能力を最大限に発揮する機会が多くある。花形と言ってもいい、憧れの部署の一員になれると思うと、シンは素直に喜びを噛み締めるばかりだった。
勿論、今後の成績で格下げになる可能性もなくはないが。
「監査は各地の機関を調査して回りますので、各人専用機と専任パイロットが必須ですが、ゴールドチャイルド社のスワニーを操縦された経験は?」
その時丁度、乗せてもらえた機体の名称を耳に、シンは踊るような気持で答える。
「あ、ありませんが、操縦系統は見たことがあります」
「そうですか、では細かな操作の説明には技師を派遣します。上官宛てに通達がありますので、配属先で連絡をお待ち下さい」
そう言えば、前に乗った時は往復とも自動操縦だった。自動操縦は外部から機体と進路をコントロールする方法で、面倒もなく安全だがとにかく遅い。VIPの送迎などにはそれでも良いが、通常の仕事には使えないシステムなのだ。
そこを素早く、安全に飛行するのがパイロットの力量。シンは一日も早く技師の説明を受け、スワニーの操縦に慣れたいところだろう。
「…就任式の後は、速やかに監査次官の執務室に出頭して下さい。それでは、忙しい任務ですが頑張って下さいね」
「はい!、頑張ります」
心からの喜びと共に、強くそう答えたシンは、もうこれまでの嫌な事件が帳消しになるくらい、吹っ切れているようでもあった。何故なら、
『干渉するなとは言ったけど、これは元首の、いやお父さんの優遇人事かな…』
そんな事実を想像できたからだ。そして、そう思うとシンは就任前にある場所を訪れたくなった。代々の元首が眠るあの場所、月の裏側にあると言うセメタリーエリアへ…
正式なパイロットに就任する前日、シンはもう一度月へ行った。
目指すセメタリーエリアは、本来一般には非公開で、何処に墓所が存在するかも正確に伝えられていない。当然その内部に入れるのは、セイジ達と一部の大臣、特殊任務を与えられたロボットのみだ。しかしシンのIDは流石に全てをパスできた。
案内ロボットの操縦で、広く荒涼としたエリアをエアカーに乗って進んだ。そこは全て元首の土地と言うことになっているが、殆ど開発せずそのままにされているのは、何か訳があってのことだろうか。或いは、原始の姿を残したい意図があるのだろうか。クレーターの凹凸と粉塵の舞う、荒々しい月の大地の一部に、その墓所はポツンと聳えていた。
そこは、実験体や実験動物の埋葬場所でもあり、その慰霊碑も立ち並んでいる。無論中にはシンやセイジのクローンの、失敗した胚なども含まれているのだろう。そして中心にひとつ、元首の墓と定められた区画があり、誰が世話をしているのか、花が植えられ綺麗に整えられていた。
深い考えもなく宇宙へと飛び出した、最初の伊達征士は未知の体験に翻弄されながらも、現世界のシステムを構築した人物だ。新造されたコンピューターの為に、一体のロボットと共に、ほぼ月とポリヴの往復で一生を終えたからこそ、彼は月に埋葬されることを望んだのだろう。
そしてそこには、後の全ての元首が埋葬されることとなった。クローン法を守る為、コンピューターと共に頭脳が生きているとした以上、その真実を知る者は殆ど居ない。だが毎年一度惑星連合の大臣の一団が、偉大な元首の追悼にここを訪れる為、墓所の周辺は常に整然と保存されている。
その墓標の前に立つとシンは思う。自分が生まれる過程からつい先日まで、自分を見守ってくれていたセッティモ、前の元首はどんな人物だったのだろう?。赤ん坊の頃はともかく、会えず終いになってしまったのはやはり悲しい。棺の中を覗いておけば良かったと、今は後悔もしていた。
自分の行動範囲に関することは、現行の形を少し変更してもらえないだろうか?。僅かな時間でも、全ての元首に触れることができるように。それと、父にメールくらいできるように。
不備を改善して行くのが今の、新しいシン・モウリの役目だと決めたのだ。
こんな、何でもない自分の為に酷い苦しみと、反動的な喜びとを持って生き続けた、全てのセイジ・ダテに哀悼を。そして、せっちゃんにもお別れを言う時だった。
『僕を愛してくれてありがとう』
と、シンは墓標の前に座り、自然に微笑み掛けていた。
『僕は少しでも君の為に生きられただろうか?』
君が、君達が僕を愛してくれているように、僕はその気持を返せているだろうか?。そうして心が繋がって行くと、未来はもっと理想的な形にできるような気がする。
『これからも、頑張るよ』
僕達の為に、地球の為に、僕は僕をもっと良く生きなければ。最後にシンはそう念じて立ち上がった。
イーストキャピタルシティ、惑星連合の地球本部は、航空宇宙局の五倍はある敷地に、荘厳な建物が広がる太陽系最大の政治拠点だ。一介のパイロットがそこに踏み入れるのは、酷い緊張を伴うだろうが、職務上それにも慣れて行かなければならない。
シンは建物に迷いながらも、どうにか目的のエレベーターを見付け出し、指示通り上官の執務室に辿り着けた。就任初日、まずはその監査次官への挨拶が大切だ。頼りないからといって、業務に直接影響はないだろうが、第一印象は悪いより良い方がいいに決まっている。
シンはドアの前で深呼吸し、着衣の乱れなどをチェックすると、確と気を落ち着けてノックをした。
「監査次官殿、新任のシン・モウリ三尉であります」
「どうぞ」
そしてドアが開くと、
「やあ。私も昇格して転属したばかりだが、まあよろしく」
そこには既に見慣れた顔が、執務室の席に着いて笑っていた。
危機から社会を守る為のコンピューターがあり、それを使い人を導く為に元首が居り、元首の精神を支える為にもうひとりの人間が必要だった。ただそれだけのことだった。
けれど人間である以上、機械のように事務的には立ち回れない。本当の意味で駒にはなれない。それを解決する為の試練から今、世界は解放され開花して行く。太古の形とは違えども、地球と、地球人が幸福に生き続けられる世界が、脈々と続くことを予感させる未来が訪れた。
それは偏に愛情の賜物。愛する世界あっての個人の幸福だ。
そして、私達の世界はこれからも続いて行く。
終
総合あとがき)と言う訳で…、お疲れ様でした。ちょっとややこしい舞台設定だったり、本当の征士と伸は既に死んでるとか、色々あって、恐らく複雑な読後の感想を持たれてると思うけど、長い時間の経過の中の様々な思惑が、万華鏡のように重なり光っているようなイメージ。そんな世界のイメージを感じてくれたら幸いです。
この話、常にリメイクしたい気持があったんですが、よく言う「頭挿げ替え」では成り立たず、キャラの性格が話に合うかどうかの点で、ずっとリメイクに至らなかったのです。今思うと結構特殊なキャラ立ての話で、かなり大幅な変更をして、どうにか無理をなくした感じです。
特に当麻は元々いないキャラで(ロボットはいた)、当麻を組み込んだ時点でテーマも全く変わりました。話の流れは同じだけど、結末として向かってる部分がかなり違います。元々SFを書きたかっただけで、大したテーマはない話だったし、その意味ではこのリメイクの方がずっと出来がいいので、当麻は入れて正解だったと思ってるんですが。
いや、どこかのコメントにも書いたけど、理屈的に結構いい加減な部分のある話だったから、それを整えられただけでも、リメイクして良かったと思ってます。リメイクと言いつつ元の文がダメなので、7割以上新しく書き直したし…。
それなりに思い入れのある作品を、こうして再び公開できて嬉しいです。長い間多分、亜細亜小豆姉さんしか知らない話だったので、苦労もあったけど今はそれに尽きますわ。
最後に、火星開拓の話が出て来たけど、原作シリーズに入る火星開拓は全く別物なので、原作シリーズを読む時はこっちの話は忘れといて下さい(^ ^;。
= おまけ =
後日シンが元首コンピューターから調べたところ、セイジの名前にある「デシモ」とは、古い言語で「十番目の」と言う意味だと判った。単純に「何世」と数えているだけなのだ。
そしてそれなら、せっちゃんは恐らく十一番目、と言う名を付けられる予定だったのだろう。父は「オッターヴォ」と呼ばれていたので八番目、亡くなった元首の「セッティモ」は七番目のセイジ・ダテ、の意味だったようだ。
しかしそこでシンは「おや」と思う。
九番目の人物にはまだ会っていないらしい。その人は恐らく父とデシモの間の年令で、「ノーノ」と呼ばれている筈だ。
ところで最近のシンの観察では、年の近いセイジは面白い所もあるが、高圧的な態度が非常に気に入らないのだ。父もせっちゃんもそんな人ではなかった。それは本人の言う通り、置かれる立場の違いからひとりひとり、個性の違うセイジ・ダテになった証明でもあるが、官僚などと言う職種に就く人間は、大体そんな人当たりになって行くものかも知れない。
そしてそれを思うと、もう二度と会うことが許されない父の代わりに、ある程度年上のセイジに会ってみたくなった。その人はもしかしたらデシモよりは、付き合い易いセイジかも知れない。
否、会ってみたい気持もあるが、面倒臭いことになりそうな気もする。大岡裁きのようなことになったらどうしよう。そもそも、自分を納得させる為に使われたのがデシモなら、その役に適さなかった人物だ。何か問題のある性格なのか、或いは既に落命しているとか…。
ノーノ・セイジ・ダテはどんな人物だろう?。
今度、トウマに会ったら聞いてみよう、とシンは思った。 終
BACK TO 先頭