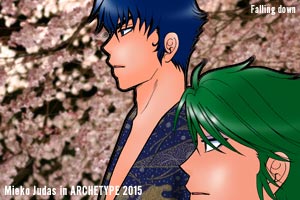 |
|||
|
朽 木 桜
|
|||
|
Falling Down
|
|||
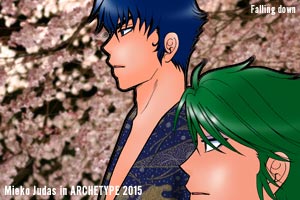 |
|||
|
朽 木 桜
|
|||
|
Falling Down
|
|||
命はその灯火が消える寸前にこそ輝けり。
萌えに萌えよ、跡に見る無惨など吾は感せず、朽木桜也。
嘗ての妖邪の都も、今は活気ある時代の面影を忘れ、うら寂しく佇んでいる。
一世一代の戦に破れ、崩落した天守閣、倒壊したままの住居や倉庫群、何の役にも立たなかった九つの塔の成れの果て。今となっては何を待ち望み、何を目指していたのかさえ霞んで見えない、人々の心の空虚さを映し出す、城と城下の街の様子だった。
然しここに取り残された人々は懸命に、建造物の修復等を行っている。働き手の少なさから、遅々として進まぬ現状ではあるが、ひとつひとつ石垣の石を組み直すような、地道な作業は日々続けられていた。それが唯一彼等に残された生業であるかのように。
そして、誰が何を思い、何をしていようと時は流れている。
不思議なことに、この土地の創造主であった阿羅醐が、永久の眠りに就いた後にもこの世界は在り続けている。強大な負の力を源とし、超自然的な繁栄を続けた歴史は失われたものの、生物がごく当たり前に存在する為の、環境的条件は変わらず残ったようだ。
また妖邪界の一日は長く、人の時も世界の時も、新たな創造を行うに余りある。これと言った希望はまだ持てないとしても、誰も明日への心配をする者は居なかった。争いの日々が過ぎ、突然この身が消滅する危機だけは免れた。今は到来した平穏且つぼんやりとした時代に、大人しく身を置き、緩やかな変化を見守るだけの営みを続けている。
それを何らかの慈悲と捉えるか、無間地獄と捉えるかは人によるだろうが。兎も角も、生き残った者には等しく、穏やかな余生が残されていた。
嘗ての煩悩京の乾の方角に、新たに建てられた『妙草庵』と呼ばれる木造の庵がある。そこには元々那唖挫の住居が存在したが、前の戦乱までに傷みが激しく放棄され、現在は鄙びた民家の佇まいに変えられた。
地上の時と比較し、六日に一度訪れる妖邪界のその朝。
那唖挫が目を覚ますと、布団の端に何やら生暖かい生物の存在を感じた。これが初めてではないので、一度眉を顰めるも、彼はすぐに普段の不機嫌そうな調子で言った。
「貴様は何なのだ、こう毎夜毎夜ふらりと現れて…」
朝の一声としては、流石に見通しの良い風情ではない。何故だか最近、夜中の内に人の布団に勝手に入って来る悪奴弥守が、昨夜もまたその奇行を行っていたようだ。
こんな気味の悪い朝を迎える度、那唖挫は「何故」と問い掛ける。然し悪奴弥守の方は、
「知らぬ」
と、いつもその理由を話さなかった。
「貴様のことを聞いている。知らぬとは何だ」
「聞くな。聞かれても何も出ぬわ」
恐らく本人も、その衝動が何なのか明瞭に説明できない、と言いたいのだろう。まあ、布団の端に潜り込んで寝ているだけで、他に何をするでもない、目くじらを立てるほどの事件でないのは確かだ。然れば、那唖挫はただ溜息を吐きながら、
「解らぬ奴だ」
とだけ返し、ゆるりとその場を立ち上がっていた。
因みに悪奴弥守の朝の態度と言えば、とにかく怠惰でいい加減な風体を現す。動作も受け答えも全てが億劫、と言う状態は、地上の人間にもしばしばあることなので、まあ容易に想像がつくだろう。そこは闇を司る彼のこと、これから明るくなって行く時間帯ほど、苦痛なものはないのかも知れない。
ただ、それを差し引いても悪奴弥守の思考、動機は今のところ解せない那唖挫だった。無論阿羅醐が存在した頃は、こんな奇行は見られなかったのだが。
常に薄ぼんやりとした妖邪界の昼間。
目覚めから暫くして、完全に陽が昇り切った頃。と言えども地上の時間では、猶に五、六時間が経過していたが、一通りの朝の用事を終えた那唖挫は、庭の畑に出て草花を弄っていた。
彼の庵の庭には、過去も現在も変わらぬ薬草園がある。よく手を入れられた畑には様々な種類の植物が、整然と列を成して植えられていた。朝方の悪奴弥守の様子とは対照的に、那唖挫は朝から丁寧に枝葉の剪定を始めていた。
そして、一部の刈り取った蔓を纏めていると、
「何だそれは」
と背後から声がした。勿論先程まで寝ていた悪奴弥守だ。つい今し方、漸く布団から起き出して来たところだった。
それに対し、那唖挫は特に振り向きもせず言った。
「草だ」
単純明快、否、さすがに不親切過ぎるその返事には、面倒でももう一言続けなければならなかった。
「そうではなく、蔓に生っている方」
庭に面した廊下に腰を下ろしながら、悪奴弥守がそう付け加えると、那唖挫は何故だか、少し愉快そうな口調に変えて返した。
「単なる草の実だ。但しこの実は面白いのだぞ、種も何も入っておらぬ。果たして何の為に生るのだろうな」
蔦に似た蔓草の所々に、熟したホオズキに似た実がぶら下がっている。誰だとして、枯れかかった蔓や葉ではなく、その赤い実に注目すると思われる見た目の様子。だから那唖挫は、無意味な果実の方に関心を向ける者には、いつも面白そうな顔をした。
「食えるのか?」
と悪奴弥守が言うと、
「食うか?」
那唖挫は相手が返事をする前に、さっさと一部の蔓を毟り、悪奴弥守の方へ放り投げていた。丁度彼の膝の上に跳ねたそれは、やや硬い感触を感じさせたが、近くに見て特に変わった植物とも思えなかった。その表面を着物の袖で適当に拭くと、悪奴弥守は何の気なくそれを口にした。
ガリッ、と、変に硬質な音がした。
そして妙な顔付きになった悪奴弥守は、手で口を塞ぎながら言った。
「何だこりゃ、皮だけじゃねぇか」
硬い音を立てたのは乾いた厚い皮、そしてその内側は、刳り貫いたようにきれいな空洞になっている。まるで胡桃の殻でも齧った気分だった。するとその様子を見て、
「だから言っただろ、何も入っておらぬと。俺は『蛻の殻草』と呼んでいるが」
那唖挫は薄笑いしながらそう話した。しかし彼が、それでも丁寧に蔓を束ねる姿を見ていると、悪奴弥守は俄な疑問を感じ尋ねる。
「何でこんなものわざわざ」
食用でも観賞用でもない。単なる雑草を畑で育てるとも思えない。果たしてこの草は何なのだろうと、悪奴弥守でなくとも普通に思うだろう。否、勘の良い人間なら、当然思い当たる節はあるのだが。
「根から神経毒が採れるのだ」
「先に言えよっ!、…ペッ!…」
「だから実は何でもないと言うに。何の役にも立たぬ」
まあ、さすがに那唖挫も、危険な物を悪戯に食べさせたりはしない。それは悪奴弥守にも判っていることだが、吐き出したのは気分的な問題だ。もう少し彼が慎重な行動をするなら、こんな笑い話にはならなかった。否、悪奴弥守はどちらかと言えば慎重な性格の筈だが、今は寝起きのせいか気が弛んでいるらしい。
まんまと思惑に乗ってくれた可笑しさか、或いは自嘲するように笑った那唖挫。
「そう、役に立たぬ蛻の殻だ。まるで今の我等のようであろう」
そして、この草の実に掛けて、何か自分等のことを語ろうとしたのだが、
「やめてくれ」
と、悪奴弥守はそれを遮っていた。それまでは頭の冴え切らない様子で、のらりくらりとするばかりだった彼が、たったそれだけの那唖挫の言動に頭を抱え、視線を伏せてしまった。
何が彼の神経に触れたのか。
だからと言って、状況の変化に気を咎める那唖挫でもない。嘗ては相手を傷付ける言葉の応酬、当て付けに見せる行動など日常茶飯だった。誰もが己の優位を主張し、他を蹴落とすことに微塵の感傷も抱かなかった。優しく繊細な情など抱えていては、魔将の立場など守れなかった。だから何を言い合おうとも、彼等にはどうと言うことはないのだけれど。
ただ、今は相手が拒絶する何らかの話を、那唖挫は敢えてしようとしなかった。目的あって罵り合うでもなければ、刺々しい会話は全く無意味だと思う。
この何もない、蛻の殻の世界では。
力の衰えを否応なく感じさせる、衰退した妖邪界を見詰めながら生きている。誰が望んだ未来でもないが、現実はそうなっている。
阿羅醐時代を思い返すと、無論後悔の念ばかりが浮かんで来るが、但しその数百年の間は、何と生き生きしていたことかと考える。剣と鎧のみを頼りに、馬を駆り、出逢う者は片端から斬り捨てて行った。ひとり倒せばそれだけ己が出世する、自由闊達で粗野極まりない戦乱の世界。それだけに余計な考えは何も持たず、ある面では幸福に過ごした時代とも言える。
ただそれが正しき道であれば。否、正しき道と信じ込まされていた我等には、今は何もかも空しい。悔やんでも悔やみ切れぬ遺恨と、後に残された抜け殻状態への嘆きが、どうしようにも心の隅に居座り離れない。まだ前世の亡霊に決別できるほど、多くの時を過ごした訳でもなかった。
恐らく、そんな煩わしい時代である今、敢えてそれを意識させる言葉を聞きたくない。今朝方の悪奴弥守の反応は、凡そそんなところだろうと、他に誰も居なくなった昼間の庵の、座敷に寝そべりながら那唖挫は考えていた。
妖邪界の昼は呆れる程長い。明るい間は全て働き続けることが不可能で、戦も休み休み行うのが鉄則だった。故に那唖挫は、一仕事終えた後の休息を取っていたのだが、そこへ誰かの足音が、庭の畑の奥より段々と近付いて来た。
特に姿勢を変えず目を凝らしていると、それは迦遊羅と螺呪羅だった。
ふたりは何を話すでもなく、先を歩く迦遊羅が那唖挫の姿を捉えると、少しばかり早足に変え歩み寄って来た。そしてこう声を掛けた。
「悪奴弥守殿はこちらに居られませんか?」
何かと思えば人探しか。
「さあ?、朝の内なら確かに居たが、その後のことは知らぬ」
「手前の庵にも厩舎にも姿が見えぬのだ、何処へ行ったんだか」
後から来た螺呪羅がそう続けたので、暫し那唖挫もその状況を考えてみる。が、
「そう言えば犬の喚き声もせぬな。何処かに遠出しているらしい」
結局その程度のことしか返す言葉はなかった。悪奴弥守の住居は都の丑寅にあり、この庵まで毎晩犬の遠吠えが聞こえて来る。犬達が活気づいて騒ぐ時は、大概悪奴弥守もそこに居ると判るのだが、そう言えば今日は静かだ、と那唖挫は振り返っていた。
今朝の様子は知っているものの、その後どうしたかなど全く知らない。各々予定を確認し合う習慣もないので、どうしようもないことだった。
那唖挫の返事に、小さく溜息を吐いて見せた迦遊羅は、
「仕方ありません、もし悪奴弥守殿を見掛けましたら、明日の九柱会合は城下の旧兵舎で行いますとお伝え下さい」
と、どうしても今日中に伝えたいことがあると話した。九柱会合と言うのは、阿羅醐亡き後の妖邪界をどう治めるか、その骨子を纏める為定期的に開かれるもので、迦遊羅と三魔将はその中心的立場だった。現在最も重要な活動である為、その内のひとりが欠けてしまうことのないよう、開催場所の変更をいち早く伝えたい。と言う迦遊羅の思いは、他のふたりにも当然解ることだった。
なので、那唖挫は畳から起き上がり、だらりとした姿勢を直して答えた。
「ああ」
恐らく、どんなに遅くとも、明日の朝にはまた顔を合わすだろう。悪奴弥守の奇行のお陰で、この依頼は確実に実行できそうだった。別段迦遊羅の役に立ちたい訳でもないが。
それにしても、と、那唖挫は明るい庭を背景にして立つ、螺呪羅と迦遊羅の落ち着いた様子を見て思う。年中気候変化の少ない、この妖邪界に昇る陽は、誰にも平等に薄ら惚けた光を注ぎ取り巻いているが、光の似合う人間とそうでない人間がいるものだと。
庭に立つふたりはそれなりに、再出発するこの世界の希望のように見える。正しき道を知っている迦遊羅、変幻自在に己を変えられる螺呪羅、そんな彼等が些か羨ましく那唖挫の目には映っていた。己にできることはただひとつ、例えそれが唯一無二の天分だとしても、それ以外何とも出来ない生き方には悔恨するばかりだ。
結局阿羅醐の誘いに乗ったのも、そこから生じる無い物ねだりだったのではと思う。何故己には他の余裕が与えられなかったのか、この身の不運を呪いたくもなる。
ここに来て見えて来た、平和な世に於ける個性の良し悪し。それもまた、長い時をかけ納得して行かねばならない、過去との決別への課題だ。
と、那唖挫がひとり想いに耽っている内、庭先に居た迦遊羅が、庵の端に並べてあったたらいを見付け、その中身が見える傍まで寄っていた。大小、深浅、幾つも並ぶたらいには洗濯物が浸けてある。迦遊羅は暫しそれらを観察し、
「那唖挫殿は意外にマメな方なのですね。分けてお洗濯ですか?」
と、正に意外そうな顔をして言った。その途端、
「ハッハハハハ…!」
螺呪羅は大笑い。続けて言われた本人も、
「はァ?、これのことか?。別に着る物などではないぞ?」
多少気落ちする物思いの後に、まさかこんなこそばゆい言葉を耳にするとは、と、乱雑に髪を掻きながら返した。
「では何です?」
「毒草を絞った麻布だ。成分が混ざると良くないのでな」
聞けば何のことはない、必要に迫られての行動だった。
「ま…。まだそんなことをされているのですか!?」
迦遊羅は言いながら目を丸くしたけれど。
そんな賑やかさもほんの一瞬。頭の良い彼女なら、その理由には難なく辿り着ける筈だった。予想通り、迦遊羅はすぐに態度を改め、
「いえ、そうですね。毒は薬でもありますから、那唖挫殿はこの妖邪界に必要なお方です」
そんな言葉を返していた。過去の日本と同じく、西洋医学など存在しない妖邪界なので、特に頼まれずとも、こうして日々備えをしてくれる現実は、広く誰に取っても有難かった。それについて螺呪羅も調子良く相槌を打つ。
「そうであろうとも。今の妖邪界が、地上に対し誇れる物が何らかあるとすれば、那唖挫の毒の知識くらいのものだ。それだけは地上の人間の益にもなろうて」
「今更誉めても何も出ぬぞ」
「ハハハハ」
ただ、前にも考えた通り、例え唯一無二の、人に取って必要不可欠の能力だとしても、それ以上に広がるものではないと言う思いが、那唖挫の頭からは離れなかった。何故なら今必要とされているのは、旧態依然としたこの世界に、新機軸を齎す発想と行動なのではないか、と感じるからだ。
九柱会合に参加する度思う。迦遊羅や螺呪羅の言動を見ていても思う。残念なことに、己はその役にはあまり立てないことを。
変えて行かねばならぬと、思いつつその能力に欠けているのが口惜しい。
阿羅醐に取っては、従順で一本気に働く部下こそ、都合が良かっただろうが。
飽き飽きするほど長く続いた晴れ間が、徐々に茜色に暮れて行く。その夕刻の劇的な変化でさえ、地上の時間にして四、五時間は続く。全く何を取っても、この世界は遠大過ぎるようだ。大地の幅は計測不能に広がっていると聞く、動植物は好き放題に蔓延っている。
それを理想とした嘗ての主の、繁栄と永続への欲求が、完全に枯れるまでにはどれ程かかるのだろう。まだ色濃く前時代の面影を残す環境を早急に、改革することは不可能だろうが、現状を何とか背負って行かねばならない、民衆の心は複雑なものだった。最早誰も大それた野望を抱いてはいない、ここで穏やかな暮しを立てるだけなら、広大過ぎる土地も長過ぎる時間も重荷でしかなかった。
また、旧都の周辺は比較的平和でも、その外に存在する何らかの脅威、過去に引き摺られたままの哀れな者達や、狂暴化した獣の群れなどに、常に警戒を向けている状態だ。負の遺産はまだまだ消化し切れない。解放された民衆には最早何も生み出さぬ、荒々しい時代がまだ一部では続いている。
そしてそれは魔将達にも、同様に頭の痛いことだった。それぞれ個人的に、忌わしい記憶から離れられぬ苦悩を持ちながら、妖邪界全体の抱える苦悩も考えねばならない。地上の歴史に比べれば短いとしても、千年と言う時間は人には荷が勝ち過ぎる。本心で言えば、身の回りの事以外は目を背けたいところだ。
離れたくとも容易に離れられぬ過去。
外に見えるものはともかく、心の内から来るものがせめて穏やかなら良いが、誰も思うように振る舞えぬのは、それ程に心に染み付いた記憶だからだ。力に服従し共に侵略の夢を見る、ある種の異常な社会での幸福の有り様が、脳裏に確と刻まれてしまったからだろう。
そしてもうひとつ、人々の不自由な心の訳は恐らく、夜の訪れが遅いせいなのだ。生物は陽を見ている間の出来事を夜に、眠りの内に整頓し忘れて行くものだ。例えこの土地に長く暮らそうと、元は皆地上の人間、その頃の精神活動を完全に忘れることはなかった。それ故誰もが、一日の終わりを心待ちにしながら過ごしている。白昼に晒される辛辣を逃れ、全てを忘れていられる夜に誰もが安堵する。
殊に大目標を失った今となっては、牢獄のような昼間をどうにか遣り過ごしている現状だ。誰もそれを表に出しはしないけれど。
それから程なく、長い一日が漸く終わりそうだと言う頃、那唖挫は部屋に明かりを灯し、ごく簡単な食事と酒瓶を膳に並べ、日頃そうするように昇る月を見ていた。
竹林を鳴らしながら吹き抜ける、生温い風が髪や肌を撫でて行く。まだ本格的な夜に入るまでは、大分間がありそうだと感じる宵の入。そんな頃はまだ、巣に戻る鳥の羽撃きや街の物音も遠くに聞こえ、酒の肴に似合う風情を醸し出している。
一日の中で、最も愉しみな時と言える夕餉の佇まい。
その時、那唖挫は廊下の奥から気配を感じ、いつもなら夜更にやって来る筈の男が、突然姿を現すのを見た。
「…今日はえらく早いな」
呟くように一言、そして次には、相手に聞こえるよう顔を上げ那唖挫は言った。
「貴様の分の用意はないぞ」
それを聞こえているのかいないのか、黙ってひたひたと歩いて来た悪奴弥守は、特に物欲しそうな様子も見せず、遠慮もなく、ただ那唖挫の座る座敷に上がると、一息吐くように体を休めていた。
何処となく、毎夜の彼の行動が窺える様子だった。恐らくいつもこんな風に無遠慮に入って来ては、休憩所代わりに勝手に人の布団で寝るのだろう。ただ今日はまだ、眠りに入るには早過ぎる時間だ。
一体どうしたことだ。
「何故己の家に戻らぬ?。折角建て替えてもらったと言うのに」
那唖挫の言う通り、ここと同様に他の魔将宅も皆、民衆の手を借り新しい住居に替えられた。以前の建物は家と言うより平城に近い、厳めしく気の休まらない構造だった為、今は今の生活に適したものに改善されている。故に、居心地が悪いと言うことはない筈なのだが。
尋ねて、暫くしても返事がないので、そこに居るであろう場所を那唖挫が振り向くと、その気配を察してか漸く悪奴弥守は答えた。
「何故と言う程でもない、俺はこっから見る景色が好きなのだ。昼はどうと言うことはないが、夜は何とも風情がある」
畳の上に片肘を突き、半ば寝そべるように外を見ていた悪奴弥守の、言葉は成程嘘ではなさそうだった。彼の視線の先には、夜目の利かぬ者には見えない、何かしら趣のある景色が見えていそうだった。
「俺には竹林しか見えぬ」
「それは残念なことだ。竹林の隙間を飛び交う羽虫のゆらめき、風に靡く黄金色の枯れ枝、夜であるからこそ美しく見えるものもある」
悪奴弥守はしばしば妙に詩的な物言いをする。そして朝方に比べ夜はよく喋った。
「今宵も、笹の葉のざわめきの上に月が昇る。懐かしいことよ、あの月は、下界に繋がろうとして繋がらなかった無情の月だ。我等はこうして拉がれたまま過ごしているが、月は変わらず高みを目指している」
まだ仄白く、頼りなげにも映る宵の月。今は悪奴弥守だけでなく誰もが、夜の訪れを待ちわびていると思うと、月を臨む景色は確かに、入り混じる様々な感情を思い出させるようだ。
地上に対し裏とも言える、この世界には日の出より宵の月が似合う。
ただ、そこまでを聞くと那唖挫は、
「下に降りたいのか?」
との疑問を投げ掛けた。悪奴弥守の物言いはまるで、月の通路が閉じたことを嘆くように那唖挫には聞こえたので。すると悪奴弥守は、
「いや…」
微妙な余韻を残しながら否定した。恐らく多少そんな気はあれど、それが一番ではないと言うところだろう。また続けて、彼の想う鮮やかな月の記憶、苦々しくも胸に焼き付いた過去の一場面の、月の交わる瞬間の出来事を語り出していた。
「今も昔も、月の輝く時は短い。身を潜め待ち続けた、我等の待望の時はほんの一瞬だったが、この空漠とした妖邪界が俄に沸いていたな、と思い出すのだ。ほんのひと晩ほどのことであったと」
長きに渡る戦乱の苦悩と憎悪の果てに巡って来た、それは打ち上げ花火のように散り行く幻。
「言ってみれば華だ」
と、悪奴弥守はその時の心境を忘れられずにいる、ようだった。
この妖邪界での過去の活動は、確かに全てその一点に集約されている。時空的にも人間界を飲み込もうと言う、彼等の悲願が現実へと昇華した短い時は、その一点であるからこそ華々しい。彼等は彼等なりに、そこから先を開いて行くことに賭けていた。だからこそ全力で砕け散った爽快感も感じられている。
また、儚き事象を取り沙汰して慈しむことは、悪奴弥守の語る美学に通ずるものがあるように思う。夜には夜の、短き命には短いなりの華やぎがあると彼は言う。
然しそのふたつの例は、同じに見えて違うと那唖挫は返した。
「だがそれは阿羅醐の為の華だ、貴様のものではないのだぞ」
「ああ…、そうだ」
だがそれでも。
過去に微笑んではいけないと解っていても、止められない感情は何処かに在り続ける。何もかも奪われてしまった今ならでは、過去の一瞬の歓喜が酷く恋しく映る。無論そんな感覚についてだけは、那唖挫も解らなくないと付け加えた。
「老木の最期の花見ができただけマシかも知れぬが」
それを耳にすると、悪奴弥守は何かを閃いたように膝を打つ。
「そう、そうだ」
そして彼はここに至り漸く、一連の話の落ちを着けるのだった。
「我等は何も知らぬからこそ、長年の労が報われる結果に歓喜した。そして何も知らなかったからこそ、今は寒々しいこの土地を見ている。あまりにこの身が寒い故、独りでは居られぬのだ」
まさか、これまでの話はそれを言いたい為の前置きだったのか?。それとも話しながら言い訳を探していたのか?。
否、と、那唖挫は一度前に向き直し、悪奴弥守が何を考えているのか今一度推考してみる。単なる言い訳と聞き流すには、叙情的過ぎるほどの言葉が惜しいとも思う。
言葉とは、時には役に立たぬ面もあるが、思考する生物には無くてはならぬものだ。今朝は何も語りたがらなかった悪奴弥守が、夜には饒舌に何かを伝えようとする。その行動自体に意味があると、こんな時には考えても良いだろう。彼の言う通り、朝には朝に、夜には夜にこそ相応しい会話がある。こんな言葉遊びのような戯れ事は、昼間は誰も大人しく聞いてくれまい。
ならば何故、戯れ事と判って話し聞かせるのか。
何故悪奴弥守は夜になると訪れるのか。
ひとつ言えることがあるとするなら、彼等ふたりには恥ずべき共通点が存在することだろうか。思えば最後まで真実を知ることなく、呪縛が解かれ、正に放り出されてしまったふたりの魔将。自ら真に気付けた朱天童子は果報者だ、彼にそれを伝え聞いた螺呪羅も、まだ納得して今を永らえるだろう。然しその他の者には、何も見出せぬまま過去は終わった。
否、まだ終わっていないのかも知れない。その記憶が足枷となり、前を向こうとする気概を削いでしまうのなら。何をしようと大した役には立たぬと、己の愚かしさを先に見てしまうなら。
受けた傷はまだ癒えてはいない。受けた無念はまだ当分消えそうもない。
それ故、悪奴弥守は何とはなしに、那唖挫の許に寄りたがるのかも知れなかった。共に有する某かの感傷がここに存在するからこそ。
「そうか…」
と、暫く間を置いた後に那唖挫が返すと、悪奴弥守は相手が何かを覚ったと見て、
「まあ今宵は、たまには酒でもと思って来たのだが」
今になって普通の言い訳をした。
解り合える者がひとりでも居るなら良い。ただひとり取り残される事態ではなかったことが、最低限の救いと彼は感じているのだろうか。今はうら寂しいばかりの煩悩京に於いて、愚か者同士がひとつ家に枕を並べている。まあそんな日常も、祭の後の情緒と言えるかも知れないが。
何れ、幾百もの夜を越える頃には、一時の狂乱に惹かれる気持も冷めることだろう。
那唖挫は茶碗に、まだ充分に重い酒瓶を傾けると、何も言わず悪奴弥守の方へと差し出した。魔将達は嘗て、相手を気遣うことなど全くしない間柄だったが、今は無礼も親しさの内に感じられている。またそれが更に、新たな関わり方にもなって行くだろう。時は残酷でもあり優しくもある。
宵から夜へと、僅かずつ色味を変えて行く天の広がり。星々だけは昔も今も変わらず、決して届かぬ希望を映すよう輝いている。阿羅醐が何を思い、この世界に星空を配したのか、今となっては不思議と理に適った創造のようにも思う。
裏の世界に輝くものは幻だ。月であれ星であれ、昼間の真実を知れば皆ただの土塊に過ぎない。
「もう、あの月には何も無いのだろうな…」
ふと悪奴弥守が、また詩的な思考に偏ろうとしていると、ここでは那唖挫が感慨もなく返す。
「何も無いままでなくては困る」
「そうか、無闇に魅力的なのも良くないか…」
幻に惹かれていては何も始まらぬ。
そうして、今宵は何にも成らぬ話をしながら更けて行くだろう。こんな日々はまだ当分続くだろう。最早花を付けぬ枯れ枝の満開を空に見つつ、いつか新たなまほろばの夢を語ることもあるだろうが。
愚か者には幸多し、とも言う。
無知は無知で、不毛は不毛で美しいかも知れない。
終
コメント)10年に発行した本を、加筆校正しました。加筆はほんのちょっとですが。
魔将単独(中心)の話は滅多に書かないし、シリアスとなると尚更だけど、この本は最初で最後?の魔将オンリーがあったので、折角の機会だから、ずっと書きたかった話を書いたんですが…。
この続きの「食」のコメントにある通り、本当はやおいが入る話なのに、長くなり過ぎるので省いちゃったんですよね。そしたら更にシリアス度が増して、すっごく真面目な小説になっちゃった感じ。いや、一度ちゃんと真面目に書こうと思ってたから、これでいいんですけどね(^ ^;
BACK TO 先頭